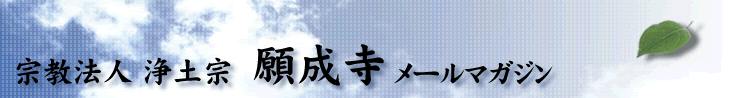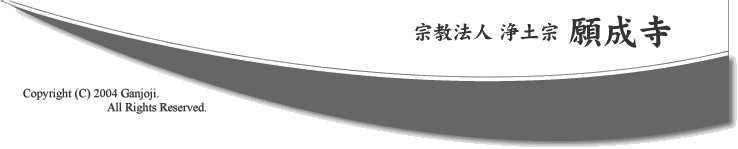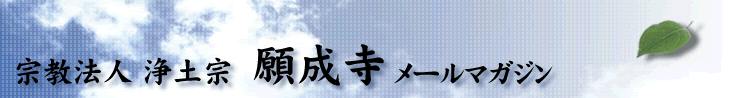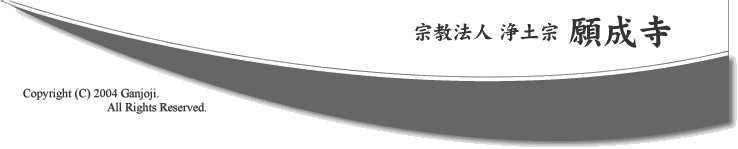|
(前話は、願成寺ホームページ「メルマガお申し込み」のバックナンバーにあります。)
桐壺更衣は、里に帰ると間もなく亡くなられてしまった。
母北の方は、亡くなった我が娘をいつまでも留めておきたかったのであるが、限りのあるこのなので葬送の儀を執りおこなう。火葬のための葬列が出発をするその時、母北の方は女房たちの車に乗り込み火葬の場への同行を決行する*。郊外東山の火葬の場にたどり着き、作法しているところみた母親の気持ちは、いかばかりであったろうか。
母北の方は、「亡骸(なきがら)を目の前にしても、どうしても我が娘の死を信じられないので、火葬されて灰となるところを拝見いたしまして、もう我が娘はこの世には亡き人と自分に言いきかせたく同行いたしました。」と、気丈におっしゃるが、車から落ちてしまいそうになる。やはり我が娘の火葬を目の前にすることはあまりにも無理であると、女房たちは苦慮している。
母北の方の車が用意されていなかったことは、本来は母親は葬送には参加しないことを意味する。逆さまを見た場合(子供が親より先に死ぬこと)には、親は葬列に参加しないという習慣からである。愛するわが子を火葬や土葬するところを目の前にするのは、あまりにも酷であるというところから発生した習慣であろうことは想像に難くない。今日でも時には耳にすることがある。
室生犀星の「忘春詩集」に「靴下」という詩がある。
毛糸にて編める靴下をもはかせ
好めるおもちゃをも入れ
あみがさ わらぢのたぐひをもをさめ
石をもてひつぎを打ち
かくて野に出でゆかしめぬ
おのれ父たるゆゑに
野辺の送りをすべきものにあらずと
われひとり留まり
庭などをながめあるほどに
耐へがたくなり
煙草を噛みしめにけり
長男を失った時の感情を静かに述べている。子供を送り出し自宅の庭にたたずむ父が、煙草を噛みしめひたすらに耐える姿が描かれている。やはり、父親は葬送には加わってはいないのである。
強引にも火葬の場までおもむいてしまった母北の方、自宅に留まり耐えがたくなり煙草を噛みしめる犀星、ともに我が子を亡くした親の心情を思うに、悲しみを共有させられてしまうのは私だけであろうか。 (つづく)
* 平安時代には、すでに僧侶や貴族たちには火葬がおこなわれていた。
天主君山現受院願成寺住職 魚 尾 孝 久
|