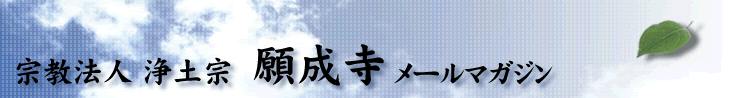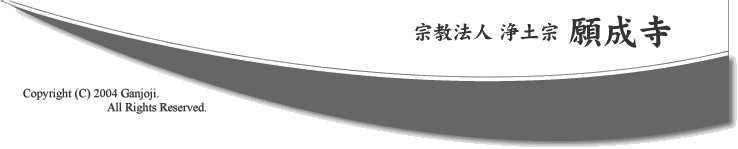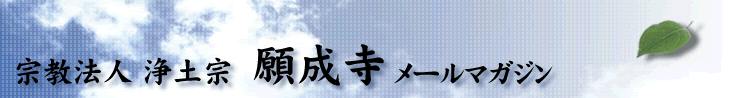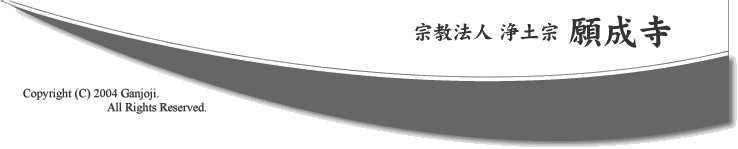|
「願成寺メールマガジン」に執筆をお願いしております土屋正道上人が、昨年10月にご自坊の観智院の法灯を継がれ、観智院第23世ご住職となられました。その折頂戴いたしました冊子「翔(しょう)−はばたきの瞬間−」に、正道上人のご祖父にあたられます土屋観道上人の書かれた「月夜の思い出」という法話が載せられております。読ませていただき、子を持つ親といたしまして、たいそう感動させられました。ご住職土屋正道上人、正道上人のご尊父にあたられる名誉ご住職土屋光道上人のご許可をいただき、掲載させていただくこととなりました。
「月夜の思い出」につきまして、光道上人は、つぎのように述べられております。
父の法話が大正11年の『真生』創刊号を初めとして沢山遺されて
います。その中で、私にとって父の思い出として、一番深く印象に残
るのは、昭和9年11月号に載った父が四十九歳私が七歳の頃の「月
夜の思い出」であります。また、多くの方からも、「あれはよかった」
「お上人の傑作だ」などという評を承ることがございますので、今回
のこの賛嘆録に再録したいと思いました。その文章に出て来る宗教
人と家庭人との問に揺れる父の心について、いくらか内容の理解を
援ける為に、そして最後に父と光道という私的な関係を超えて、皆様
御自身への父の心を、そして仏様の愛を受取って頂ければと思いま
す。
是非とも、お読みいただきますことを念じております。
「月夜の思い出 」
観智院第21世 土 屋 観 道 上人
八月の頃であったか、私は或る日の夜、長男の光道と云う今年七つの独り息子を二階につれて上った。
丁度湯上りではあり、それに二階はそよ風が吹いて、非常に涼しい気持ちのよい晩であった。折から月が南の縁側から座敷の中にのぞきこんでいた。
「光ちゃん!あのお月さまを御覧なさい。いいお月さまですね!」
こう云って、私は光道を私の手もとに呼びよせた。そして私は、丁度月の見える所の縁側近くの畳の上に、ごろりと横になって、片ひじをついて、西を頭にして横になった。
「おとう様、いいお月さまですね!」
かれは静かに月を見入って、こう云った。その時彼はもう私のそばへ来て、私にだかれていた。そして勿論、私も彼を引きよせて、静かに彼をだきしめていたときである。
私はどう云うものか、此の子がひとしお可愛くてならない、そして何とかして此の子に永遠の真の幸福を与えたい。私自身に幸福を与える力は無いが、今私の感じているようなこの幸福、それは云うまでもなく、此の広大無辺な天地の中に充ち満ちている如来様の慈光、而もその裡に永遠より永遠に生きることのできている此の仕合せ、此の幸福、それを私は此の子にも判って貰いたいという、その願いであった。
今夜と云う今夜は私には何の不安も無かった。否、私には此の子、光道を見るとき、どんな苦しみも私には忘れられるようである。子を思う親の心と云うものは誰でもそうかも知れないが、近頃の私はそのことがつくづくと感じられてならない。
私は永い問、二十歳前後から宗教を求めて、それに没頭し、殆ど最近までは人生と云うもののすべてを之に費した。だから此の外には私の人生は全くないと云ってもよい。尤もその中には御飯も食べた。伝道もした、又私の気に入った妻も得ることが出来た。しかし乍ら、それも私の道を求める心に此べればものの数にも入らぬものばかりである。之等は皆私をして云わしむれば、ただ人生道中の一つの出来事にすぎない。
然るに、此の光道に対しては、私はそうした感じを起すことが出来なくて、特に此の子を思う至情の余りに深いのに驚いている。
そう云えば他の子供はどうかと云えば之も亦愛してない事はない、光道の上に二人、光道の下に二人、合わせて女の子のみが四人いるが、これとても一々それに接し、その間の愛を思えば、一人として親の至愛に区別のあろうはずもなく、又どれとして、親愛の浅からぬものとてはない。けれども、五人の中にたった一人の男の子、どうしたものか彼は私を心から慕ってくれる。子として親を慕わぬものはあるまいが、五人の子供の中で、彼は特に私を専心に慕っている。かと云って、それだから私は彼を愛すると云うのではないが、どうしたものか、彼ばかりは私の手ばなすことのできない至愛の中にある。
私は今もなお、毎月の半分は外出して家にいないのが常である。その為めに親しく子供に接することができないのと、又家に帰っては朝夕の仕事、仕事と云っても、全く宗教のことのみではあるが、その為めに殆ど二階に昇りづめで、ゆっくり子供の相手などする暇がない。その為めに子供の教養には今少し時間が欲しいと思うことも度々である。こんなことはどこの家庭でも同じだとは思うが、特に、仕事を外にのみ持って、家を不在にする人の家庭に限って、多くは不良の子の出来るのをよく見る私は、近頃一層心して自分の子供を見るようになった。
「あわれ、人の子と生れし此の子達、お前等もこうして人の子として生まれて来た。それに何の因縁あってか、お前等はたくさんの人と云う人の中にも、ただひとり、吾等夫婦を親として生れて来た、それなのに、此の父は如来の使命を果す為めとは云い乍ら、ろくに父の慈愛をお前達にゆっくり与えることの出来ぬのをすまぬと思う」と私はこういうことを此の頃時々、之等の子供に対して感ずることがある。
一家をたった独りの妻にまかせきりで、経済のことから子供の世話まで、その一切を妻に任せて私は殆ど全部を伝道に専従している。
しかし乍ら、「こう云うことは果たして人として為すべきことか。そしてまた、果たして多くの人々が妻子ある身で為しうることか。妻の身としても、或は堪え難いことかもしれぬ。又子としても必ずしも仕合せではないかも知れぬ」とこんなことさえ思うことがある。
本当の意味から云えば、せめて朝夕は無論のこと、時に月一日なり、二日なり一家が揃って外出もし、或は喜びを共にする夕食の膳にもつき、時には一家揃って仏前に念仏すると云うことが一家の中の理想ではないか、家庭の平和、家庭の楽しみ、私はこうした中から、国家の為め、社会の為めに真に働く人物も出るかと思う。
そう思うと、私の如きはあまりにも理想高きにもかかわらず、甚だ実践の伴わないものである。だから昔から宗教家は独身を以て、一生を終るべくせられたのではあるまいか、それは之等の妻や子に対しても自分の責務が尽せぬからである。又それかと云って、妻や子の為めに自己が捕われて、自分の本務を忘れ、真実の伝道も怠るようでは之また宗教家としての道がとれぬことになる。
こんなことを思うと、私は今更のように、「私のような人間はやっぱり妻をも娶らず、子供も無い方がどれ位よかったか」と思うことさえある。そしてまた、それ丈けに、自分の不徳を妻と子に対して、人知れず済まないと思うことも重々である。
けれども、こうしたことは恐らく私ばかりではないかもしれぬ。凡そ、人として、いかなる人も、幾分か此の考えのない人はないかと思う。それは凡てが凡夫の生活であり、又働かねば食えない今日の社会である。食う為めの人生でないと云うことはもとより承知ではあるが、そこまでに行かない人は自然に食う為にもその家をあけねばならぬ場合が多く、それでなくても何事かを為さんとする人々は一そう家にばかりいて真の仕事ができようわけもないのだから、大きな仕事をすればするほど、又自ら家を空にすることの止むなきものがあることはやはり私と同じであろう。
私はこう思うとき、やはりこう云う人々も私と同じく、その妻子に対する充分のつとめを事欠くことがあるのではないかと思うことがある。
かと云って、今更ら独身にもなれない。独身になれば反って、それ丈け一層妻子に対してもすまぬことともなり、それに比べれば、まだ今のままの方がどれだけましか知れないからである。
そしてまた、そればかりではない、こう云う私が一家の為に、一家のおかげでどれ位心の底から此の人生がなぐさめられつつあることか。一家の楽しみ、一家の団欒、それは何でもないようなことであるけれども、心から全身を献げてくれる妻の至情、他人から見れば取るにも足らない、嫌われものの私ではあるけれども、心をこめたるその妻の情け、子供の信頼、之等は天下何ものと云えども之に代るべきものはない。
それにまた、夫として妻を思うことのできる心、親として子を思うことのできる心、こうした一家の中に身心を忘れて心の底から安らぎうるものは何と云っても家庭の外にないのではないか。私はこういうことを今つくづくと感じている。そして、私は「私の宗教はやっぱりこれでよいのではないか」と思っている。否、「之でなくてはならぬのではないか」とさえ思っている。
私は三十四歳の結婚であった。晩婚と云うことは少々云い過ぎかも知れぬが、子供の為にはむしろ晩婚と云わねばならぬ。そしてそれだけ今や余命も少ないと思う一人である。
未だ五十にもいたらぬ者が今から余命なぞは何事だと云う人があるかも知れぬ。然し静かに人間の一生をふりかえって見れば、人生の二十年、三十年と云うものは実に夢のように過ぎて行く、殊にここ二十年の過ぎたことのいかに速いかを思うとき、私の一生、それがよしまだ十年二十年あったとて、それはまた実に夢のように速いと云わねばならぬ、こうした意味で、私は近頃、実につくづくと人生の無常を感じている。
尤も此の無常と云うは信仰に入らない以前に考えていたような無常では毛頭ない。死を恐れるの無常ではない。もうすぐだぞ、ぐずぐずしていると遅くなる、為すべきことも何もできぬと、何となく旅路が急がれてならぬ感じがする。秋暮れて冬近づくの感じである。
春は春を楽しみ、夏は夏を楽しむように、秋は秋を、冬はまた冬を楽しめばよいことではあるが、それならばまたそれでよいとして、私は此の人生の春秋を心ゆくまで楽しみたい。
人生を楽しむと云うは如来を中心として、一家団欒に、社会も国家も人類の幸福のために挙げて真実の生活にはいることである。而して、今はまだその時でない、今はただ工事工策の最中である。そこには大なる努力を要する。あらゆる人類の覚醒を促し、奮闘以って此の身を致すべきの秋である。
それでも私は近頃、それもここ六、七年の事ではあるが、時々私は自分の家に帰ることにした。そしてせめては此の時間のうちに、心から家庭の生活に入りひたり、妻子への務めも果そうと努力した。
もとより、外への活動も理屈から云えばそのまま、一家の一員として、又同時に社会国家の一員として、自分の為すべき仕事ではあるが、それは暫く、とに角として、一つの務めでもあり、また一つの楽しみとした。
「光ちやん、あのお月さまがああしてお空に輝いているが、今ここばかりを照らしているのではないよ。どこもここもお月さまの照らさないところはないのだよ」
私は月を見ながら、実は月の事を考えていたのでは無かった。
天地の充つる如来のみ力、そのお慈悲の輝いているのを見て、それに入りひたっている、その光りのことを私は云ってた。然し乍ら、此の月の光を受けて、尚その月の光に気がつかない人のあるように、まだ、此の如来様の光を見ることのできない此の子に、私は謂い知れぬいたわしさを感じざるを得なかった。
此の子がいつになったら、私の此の心が判ってくれるだろうか、此の月の光に照らされて、此の月を見入っているように、ジッと如来様のお慈悲に入りひたるときが此の子にいつ来るであろうか、私はそれを知らない、その親心を知らない此の子をいじらしくも静かに抱きしめた。
彼はピッタリと私によりそって、いかにも満足げであった。そして、その月の側にかすかに輝いている一つの小さい星を見出して、何か考えていたようであった。彼は、
「お父さま!あそこに小さいお星さまがあるのね!あのお星さんもやっぱり世界中を照らしているの?」
「そうよ、あれもやっばり世界中を照らしている、遠いところにあるからこそ、小さく見えるが、実はお月さまよりもずっと大きいんだよ」
「ふうーん、どうして小さく見えるの?」
「遠くにあるからよ!人間だって、遠くにいる人は小さく見えるでしょう。飛行機だって、遠くになるとやっぱり小さく見えるでしょう、それと同じですよ」
「うん。」
「それと同じに、お星さんもお月さんよりずっと大きいんだが、遠い遠い所にあるので、あんなに小さく見えるのだよ」
「おてんとうさまもやっぱりそうなの!」
「やはりそうです。お月さまと同じ大きさに見えるけれども、お月さまよりずっと大きいんですよ」
光道は何を思ってか、しきりと月を見ながら、太陽のことを考えているらしかった。
「光ちゃん、此の光の外にまだ色々の光があるんだよ、その中でも如来さまの光というものがある。光ちゃんにはそれがまだ判らぬでしょう。お父さまや、お母さまがこうして光ちゃん達を可愛がるように、此の世の中には如来様というおかたがあって、いつも世界中のものを照らしてこれを可愛がっていて下さるのですよ」
こう語り乍ら、私は天地に満ちている如来様の慈光について語って聞かせた。大ミオヤの光にひたっている自分の幸福を感謝すると共に、いつになったら此の子にも此の如来のみ光を感じて貰う時があるかとつくづくと考えざるを得なかった。
「光ちやん!お父さまがこうして光ちやんを可愛がっているのが判るの?」
「判るよ!」
「どうして?」
彼は暫く考えていたが、ややおどけを交えて、嬉しそうに、
「ぼくがお利こうだからよ!」
と云って私によりそった。
私も嬉しくて抱きしめた、けれども、いかに私が彼を可愛がっているかは恐らく彼はまだ充分には知らぬであろう。
然し乍ら、私はこうして、此の子供を抱き乍ら、願わくは此の子が大きくなって、
「自分の父はとても私を愛してくれた」とそのことをしみじみと思い出してくれればよい、そしてその時こそ、「父がああしてまで私に父の愛を知らしめようとして、而もそれは、父が自分がよく思われたいがためでなくして、この私に仏様の愛を充分に受けさせたいがためであったか!」と思ってくれる日の来たらんことを念ぜずにはいられなかった。
私はかくて、子供が大きくなるにつれて、どうか如来様の御恩を忘れず、又この両親がいかに自分達を愛していてくれたかを衷心から喜んでくれる日の一日も早く来らんことを願って止まなかった。
何だか此の一夜は、此の月を見て深く考えさせられる一夜であった。
|